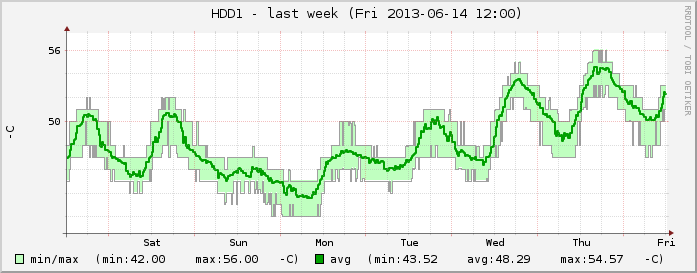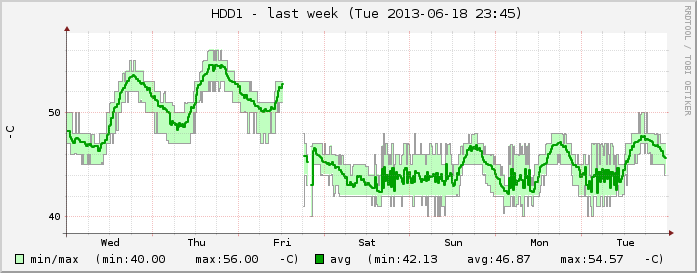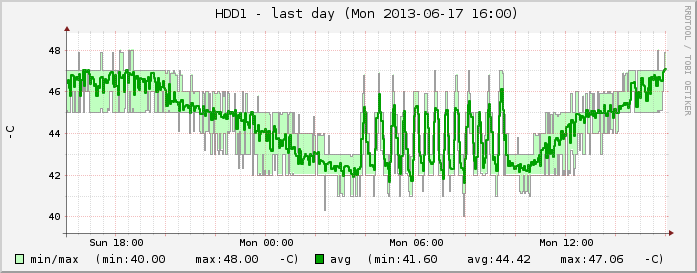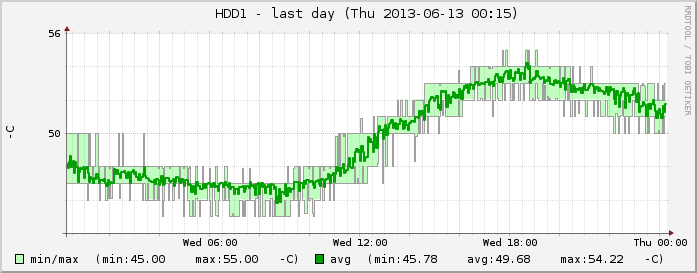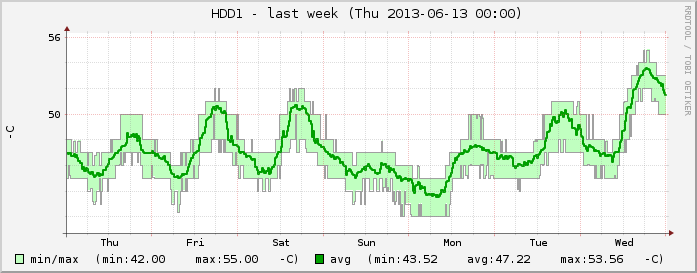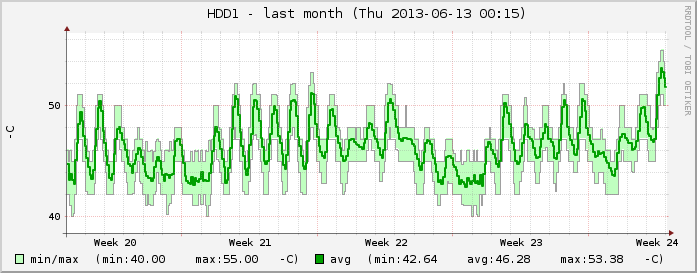アーキエイジのCBT(6/26~7/4)に応募したら当選したのでやってみた(公式)
ゲーム内容については紹介サイトがあるので気付いたところだけ簡単に書く(ArcheAge総合情報サイト・4Gamer.net)
動作環境
著者はWindows XP Professional x64 Edition(以下XP64)をゲームPCとして利用しているので当然XP64でやりたかったのだが、公式の必要動作環境にはXP(SP3以上)の記載はあるがXP64はない
しかしおそらくは32bitコードだろうと思いX64でセットアップしたところ残念ながらSP3ではないと弾かれてしまった(XPとみなされたみたい、XP64はSP2まで)
しかたがないので別のPC(XP)でセットアップ、起動するとパッチ(クライアントのDL)が開始して約30分待たされた
- 最初のセットアップで、デフォルトのフォルダーから別のドライブを指定するとエラーとなる(別のドライブでもフォルダーを指定するとOK、これは不具合だろうな)
- 初回パッチ時のDLサイズは展開後約20GBであるが40GBの空きが無いと容量不足ということでフォルダー指定できないようになっている(将来を見越しての40GBということなのだろう)
実行したPCは初期のCore i3 2.9MHz、メモリ4GB、Geforce450の旧スペックであるが、画面の精細設定(最小、中間、最大、超最大、カスタマイズ)の最大でも十分に動作した(画面は1680x1050、CPU使用率は60~70%位)
- 画面の設定には他に全画面・Windowモード、DX9とDX11の切り替え、マルチスレッドモード(だったかな?)がある
- 当然DX11はOSが7以降(VistaでもOK?)で、Geforceの場合400シリーズ以降でないと使えない
- 画面の詳細設定の内、最小は確かに画質が荒く見えたが、中間以上はほとんど変わらない(グラボの問題か?)
- DX9でもかなり美しいグラフィックを通常スペックのPCで実現している(CryENGINEの威力か?)
(X64での動作)
XPにて最初のエリアは問題なくしかも快適に進行し次のエリアも途中まで問題なかったのだが、タワーシティの手前あたりで突然「エラー」と表示され終了してしまった
異常終了は開始してからこの時が初めてでベータ版だし偶にはあるだろうと気にせず再度起動して進めようとしたが10分もたずに同様に終了してしまった
メモリ使用状況を見ると最大の2GBとなっていたが、プロセスは4,5つかな?に分かれている(最大でも700MBだった)のでユーザメモリMAXということではないようだ
その後も何度か起動するが数分(起動直後もあり)で異常終了してしまうのでは流石にプレイにならないので諦めることにして不具合報告
次の日公式を見るとパッチのDLが正常動作しない人のために直接クライアントをDL出来るようになっているのを発見
もしかするとXP64でも動作させることができるかもしれないと思いさっそくDLして起動してみたら問題なく動作
その後はXP64で続きを進めCBT終了まで異常終了することはなかった
XP64でのメモリ状況を見ると2.6GBまで使用されていたので、XPでの問題はもしかすると使用メモリが2GBを超えたところでスワップできない状況が発生したのではないかと思われる(通常ならOS不具合)
いずれにせよ(64ビット環境の方が無難な位としか言えないが)32ビット環境では動作が危ういと思われる
XP64も正式対応に入れて欲しいと願う
キャラ作成
最初に西と東の大陸(ヌイアとハリハラ)のどちらかを選択してキャラを作成
- 顔の形を設定するパーツが多く個性あるキャラにできる
- 西と東は敵対関係なので友人等とか一緒にプレイする場合は注意(初期ではお互いにチャットもできない)
- 種族固有のパッシブスキルによって僅かながら専門となる行動に差がある
- 大陸構造もまったく同じというわけでなく経路の違いにより交易のやり易さや農作物の適正気候の地域数が異なる
- 初期に入手可能な搭乗用ペットが種族によって異なりペットの移動速度、能力に差がある(ペットはどの種族のものでも搭乗可能であるが、初期では同一大陸内のペットのみ入手可能)
全体的に西の方が有利にできているのではないかと思ったが、著者はハリハラ大陸のハリハランを選択
尚、キャラの雰囲気はそこそこでガキっぽくない(20~30代の雰囲気)
クエスト
この手のゲームはログインした後、まず何をするかで困る(著者は画面設定と操作設定を行ったが)
しかし目の前のNPCが「マウスで移動するには操作設定で変更」と言っているので、とりあえずマウスでの移動をONにしてNPCを選択(会話となる)
さっそくクエストが始まり対象NPCへ移動してクエストを完了、すると続けてクエストが始まるといった連続クエストになっていた
また、そのエリアでの最後のクエストの完了が次の新しいレベルアップしたエリアのNPCとなるので、クエストを続けていけば主な都市を含むエリアを回ることになりゲーム内の設備を知ることができ、同時にゲーム内でできることをクエストを通じて学習、キャラもレベルアップするようにできている
- クエストをこなしていけば先に進む形になっている
- 女神転生オンラインのようなシナリオクエストもある
- 30レベル位からのエリアはPK可能なエリアになる
- クエストは必ずしも達成しなければならない訳でなく、必要なクエストだけやるとか無視して先に進んでも構わない
職業
キャラ作成時に職業を選択するのではなく選択可能な3つの適正を保有した時(3つめはLv10に選択可能になる)に職業が決まる
適正には複数のスキルがありレベルアップで取得するスキルポイントを使ってスキルを有効化する
有効化したスキルのみ利用できることになるのでスキルポイントの取得が重要となるが、スキルポイントはLv50になっても全てのスキルを有効化できる数にはならないそうだ
そのため全120種の職業の中で同じ職業でも選択するスキルによって異なる能力になりキャラに個性ができる
スキルにより装備する武器や防具能力の差はできるが、装備するものが決まってしまうような概念はない(例えばWIZが短剣を使って攻撃しても良いし、弓に特化したキャラが盾を持って防御しても効果はある)
労働力
狩りや戦いは除いて、採取や栽培などの行動や何かを製作するときに決まった数の労働力が消費される
- 労働力が0だと大抵のことは出来なくなる(移動や会話はできるけど)
- 労働力は時間経過で回復する(ログインしていなくても回復)
- アイテム課金(労働力を課金)というのにでも使うのかな
装備
ややこしいから省略
PT
初期から始まるクエストはソロで十分に戦えるが一部PTの必要があるクエストがあった(クリアしなくても先に進める)
- PTはリーダー(PTL)が存在し編成する
- 編成はチャットの名前から右クリックメニュから可能
- 最大5名(クエストで3名までと制限ある場合もある)
- PTリストを右クリックするとメニュが出てターゲットを合わせることもできるようだ
攻撃隊
多人数による戦い(NM討伐、PVP)では攻撃隊を編成するのと便利
- リーダーが存在し編成する
- 編成はチャットの名前から右クリックメニュから可能
- 最大50名となり全員の名前とステータスがリスト表示される(表示枠はPTより小さい)
- 1名づつ招待していくが、編成は自動でPT(1PT5名の10PT)に分かれているようである(PT向けスキルは全体には反映されないと思われる)
- PTの移動はリーダーが自由に行える
- 回線異常でログオフしても攻撃隊から外れずログインすれば復帰する(その間リストでログオフなのが判る)
- リストからメンバを選択すれば個別回復などはPTを超えても可能
PVP・GVG
- エリア単位で状態が切り替わり平和状態以外になるとPVPが可能になる(低Lvエリアは平和状態を維持)
- 同一大陸内のキャラはお互いに仲間であるため通常の攻撃は不可で強制攻撃にて攻撃可能となる(暴力行為、倒すとPK行為となる)
- どのエリアでも対戦要求でPVPが可能(PKにはならない)
- 海洋とフリーダムロード(島)、海賊島は常にPVP可能の状態
- 平和状態の場合、相手の大陸にいくと先制攻撃はできないが相手からは攻撃を受け攻撃されたキャラに対してのみ反撃可能となる
- 倒された場合、ルイの女神で復活する(PVPの場合は経験値が下がらないようだ)
- 連続して倒れると復活までの待機時間ペナが発生する
- GVG時、戦力差などで一方的に倒された場合、同じ場所のルイの女神で多数が復活するため敵側に囲まれて膠着状態になりやすい(欠点だね)
総評
栽培、製作、グライダー、船、トレジャーなど、他にも多くの楽しみがあるが一週間程度では試すことはできなかったが、1つ1つのコンテンツの規模から生活型MMOであるというのが良く判る
しかし、戦闘型のMMOで主プレイする人もいてPKerの道に進み海賊に落ち着けば良いが、そうならないようだと日本でのユーザ定着は難しいかもしれない(PK可能エリアも限定されているのでなんともいえないかな)
(陪審員制度)
- 無罪は良いとして有罪5分からというのと、最高が犯罪ポイントによる最高値であるのというのがつまらない
- この甘い(PKを数回やっても20分とか)判決のため、最高でも知れているので被告側も慣れてしまえば弁護などやらない
- 実際、CBT最初の頃は余興もあってか被告と陪審員の間のやりとりがあったが、後半ではやり取りは皆無となり陪審員側もわざわざ行く必要もないので召集を拒否するといった結果になったと思われる(つまり一週間で飽きた)
- 例えば有罪なら最低60分~で最高を1日位(犯罪ポイントで最高を日単位に上げる)にするようにして(無罪と最高は陪審員全員一致で可決)被告側が刑を必死で最小にするように仕向けないと余興にもならないだろう
- また刑務所での拘束時間はオンラインでないと減らないと聞いたが、放置はサーバ接続と電気代の無駄なのでオフラインでも減るようにすれば良い
(生産物)
- 生産物は使っていると耐久が減っていくが、壊れないでゲーム内通貨で修理できるようだ
- 食材等は生産物が消費される問題ないが、装備や機械などの生産物は飽和してしまうのではないだろうか
- 壊れた生産物を材料にして作り直すとか材料がないと修理できないようにしないと生産物が飽和状態なり一次産業は崩壊してしまうとう懸念がある
(地価)
- 家や農園をどの場所に設置しても税金は同じだったと思える
- NPCの近くに農園を設置する方が便利なので当然取り合いになる
- 設置場所により税金に差をつける方が良いかと思う
(交易)
- 内陸交易と外陸交易の差が少なすぎるではないだろうか
- 参考で2~3倍くらいの差しかないのを見たが移動の時間や略奪の危険を考えるとリスクに見合わないと思う
(気象効果)
- 例えば、海の波は非常に綺麗にできているのだが、実際の海の波とは異なりどこもかしこもプールの波のようである
- 技術的には厳しいのだろうが、荒れた海とか表現し船の航行にも影響がでると良さそう
(天災)
- 地震、火山、津波、台風など稀に発生して破壊されるとリアル性が増すのではと思う
- それに合わせて家など強度を付ける(高い強度の家は、材料数や材質が異なるとか)
(進化)
- これは新しい乗り物とか出てくるのだろうから実装されているかもしれない
- 例えば、大陸(国)単位の競争になるが、大陸が発展(大陸内の生産数や通貨量に応じて)すると進化した装備や乗り物が発明され設計図が手に入るようになるとかである