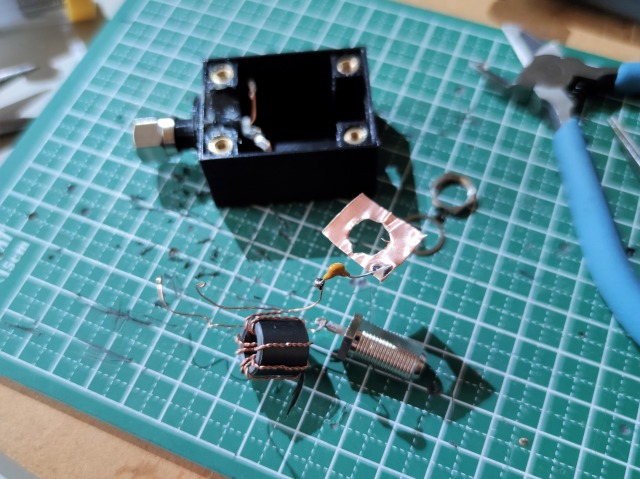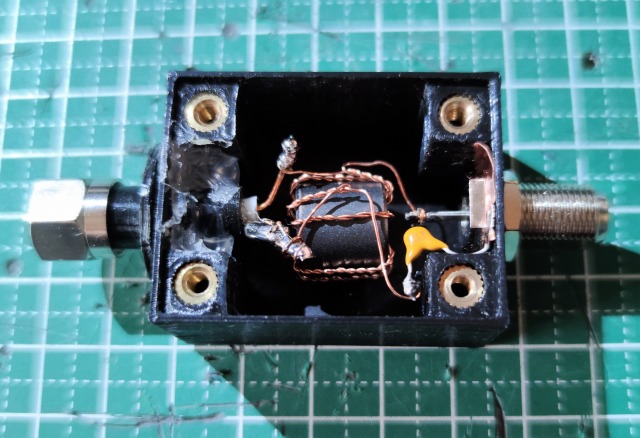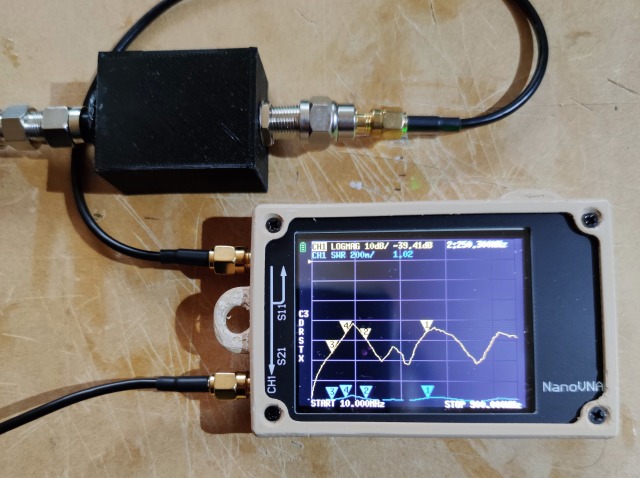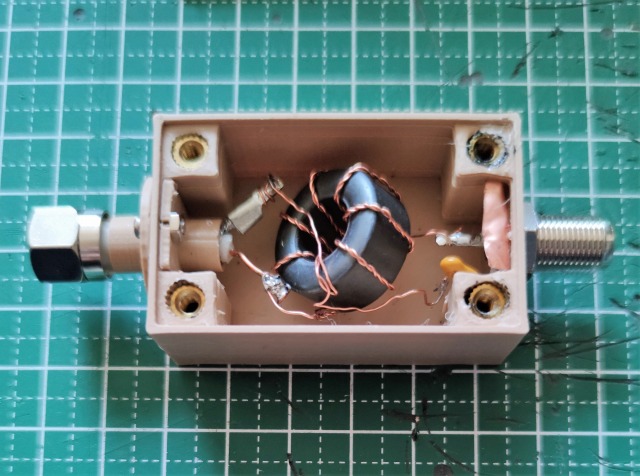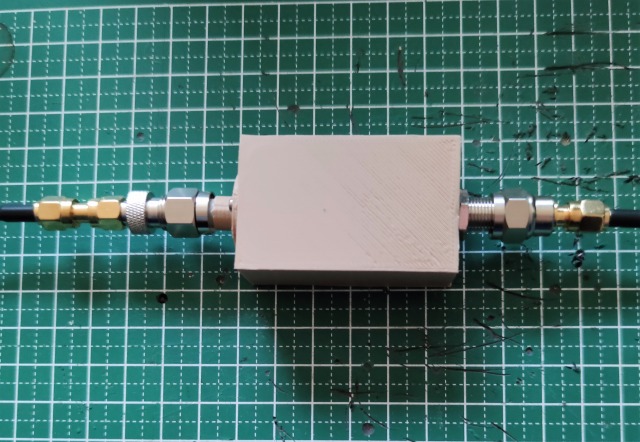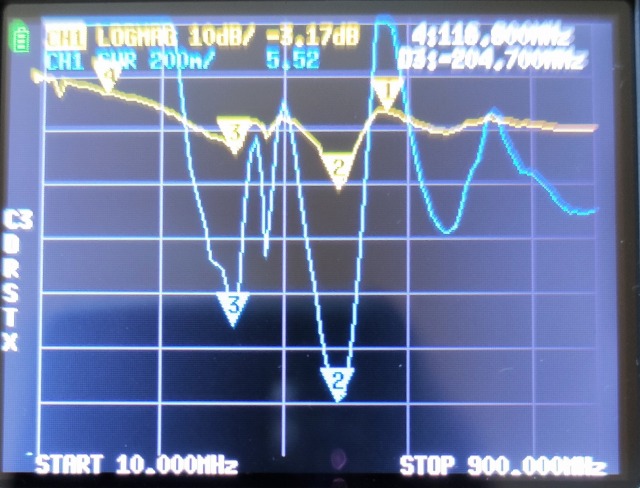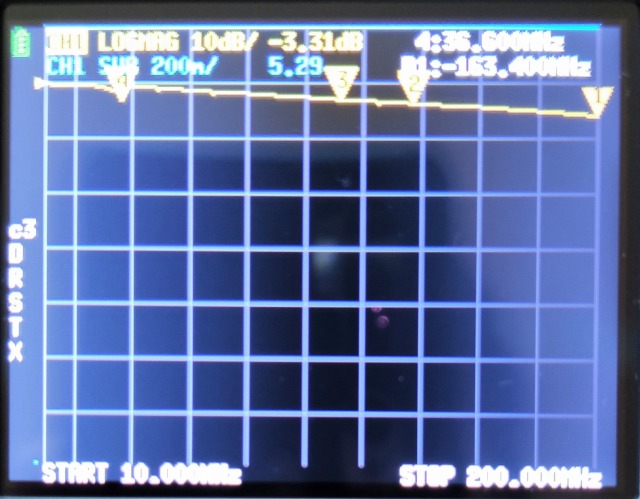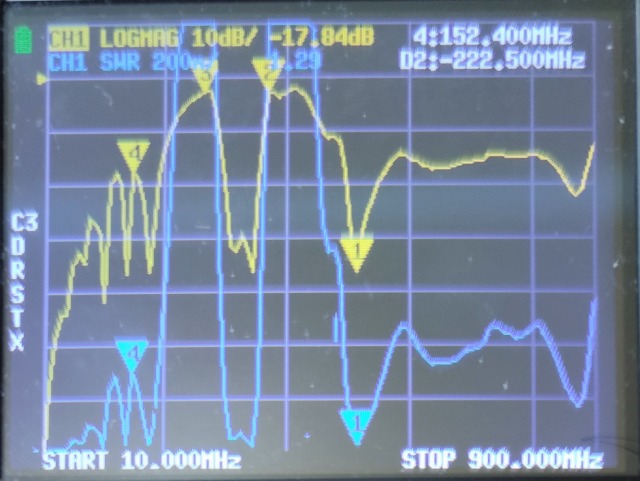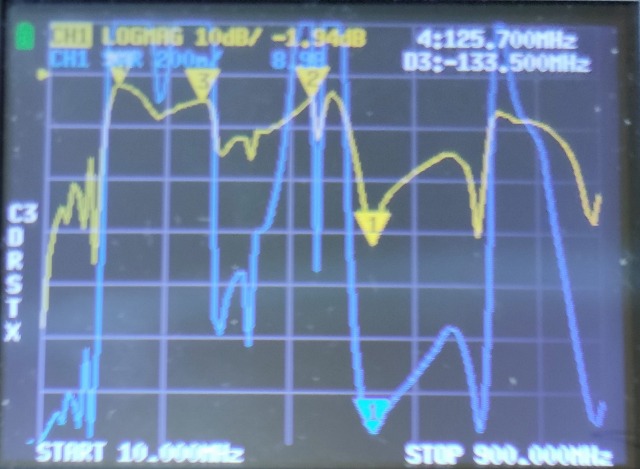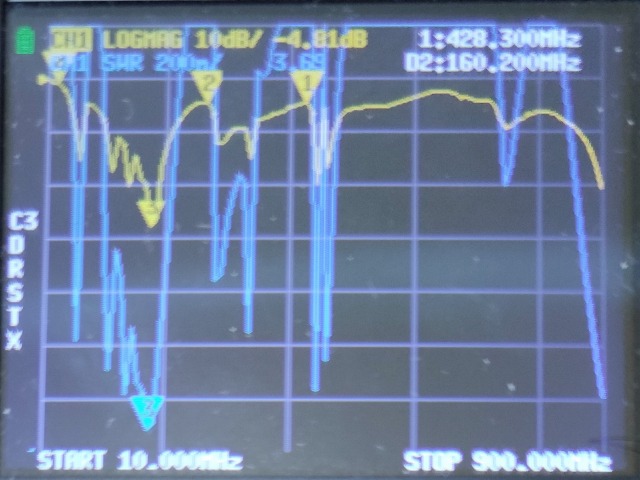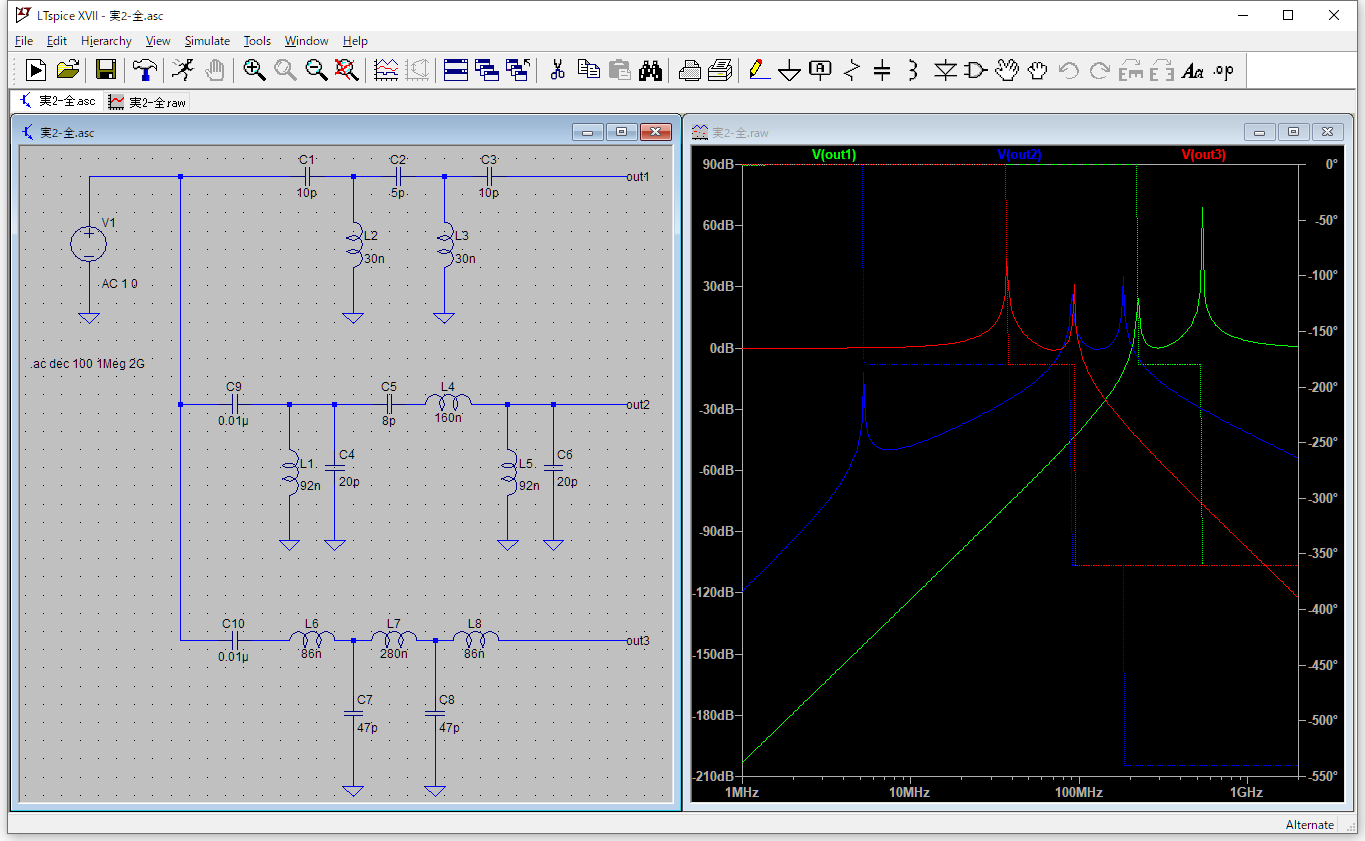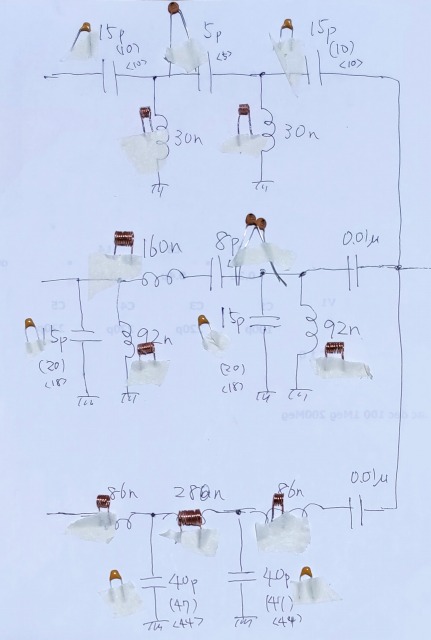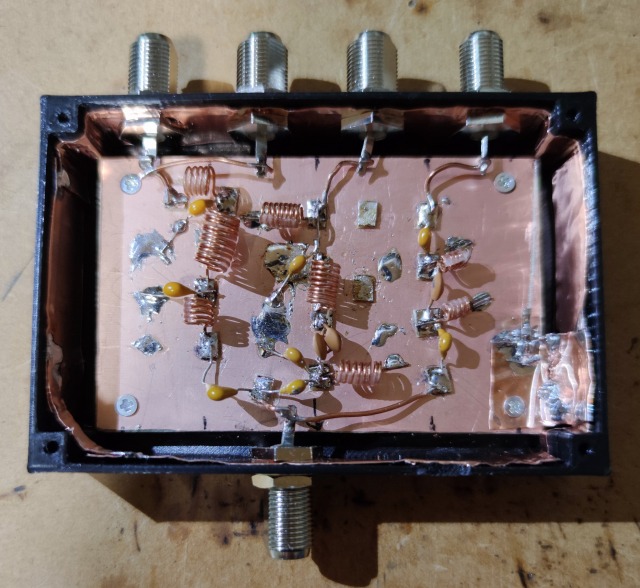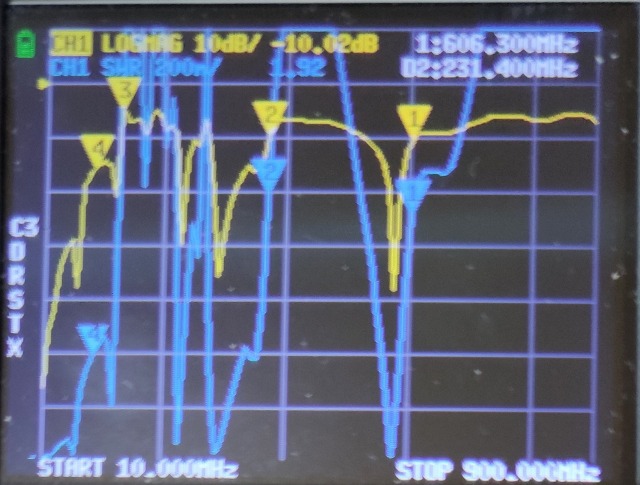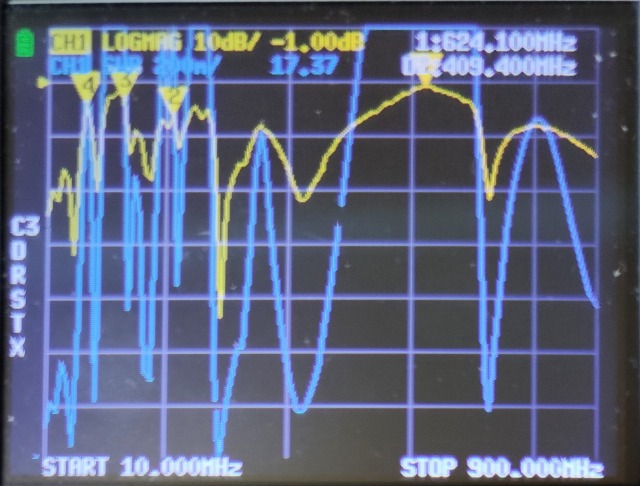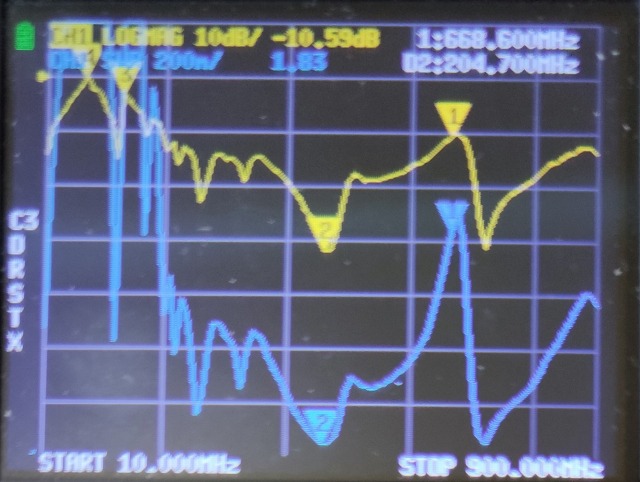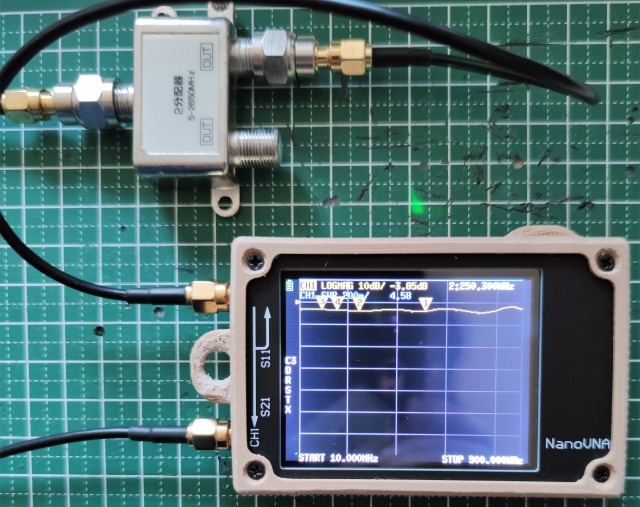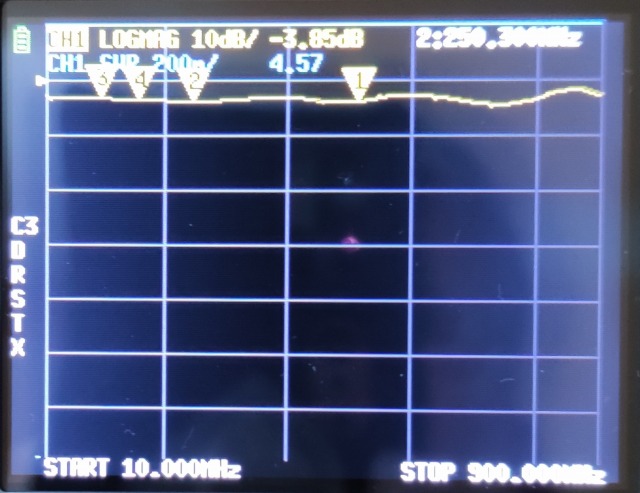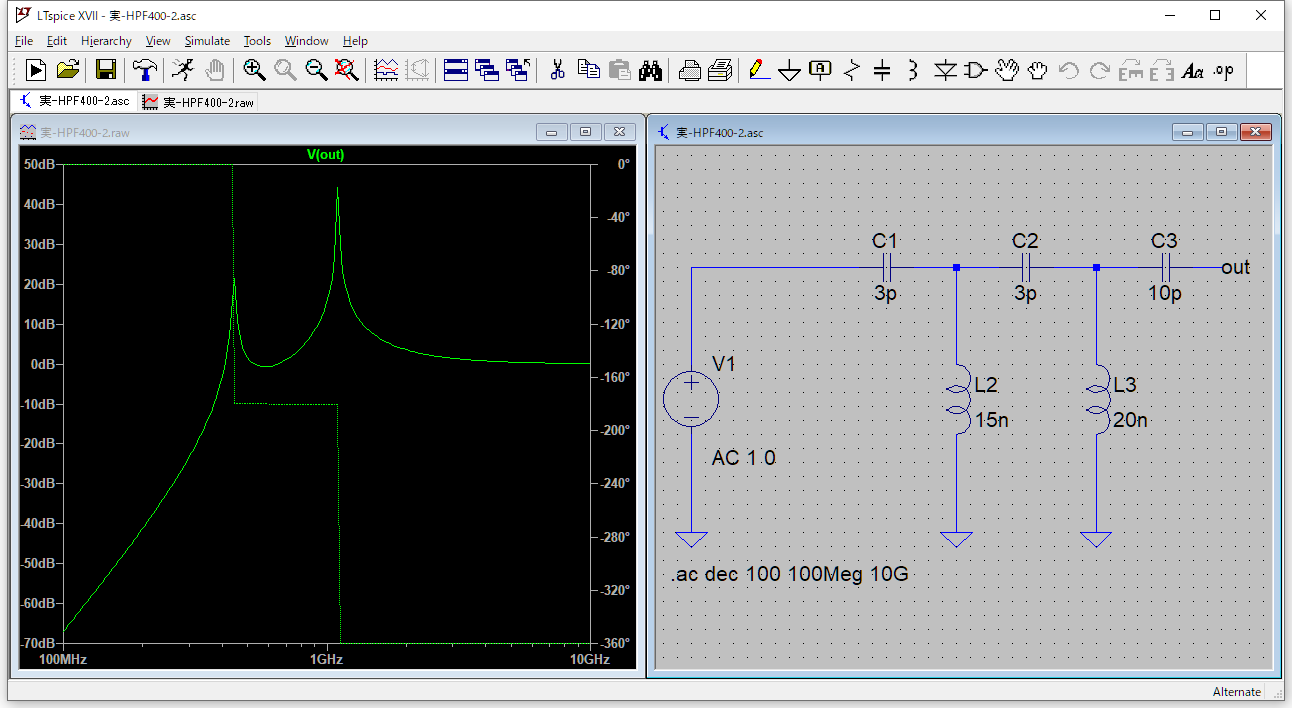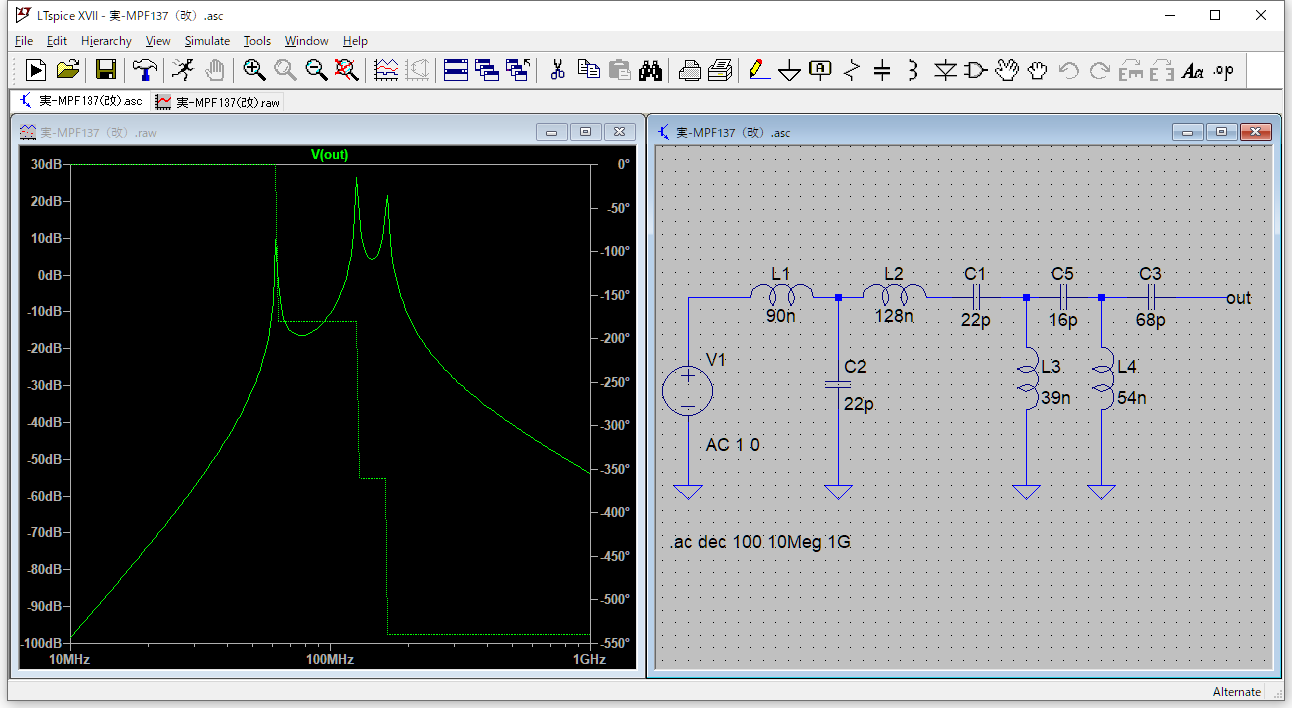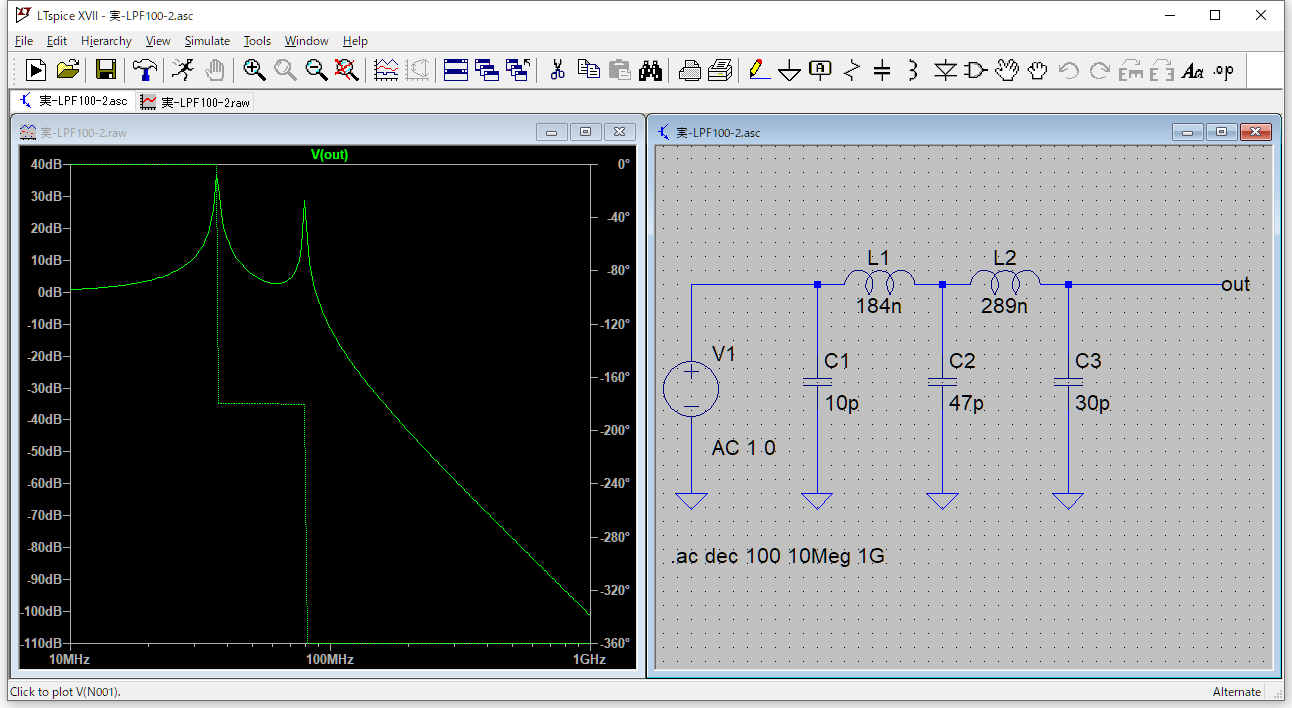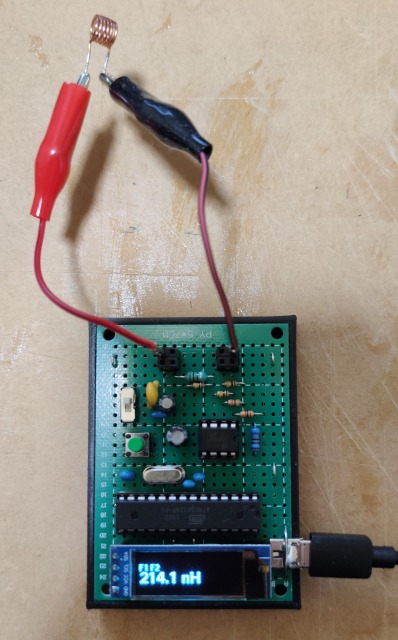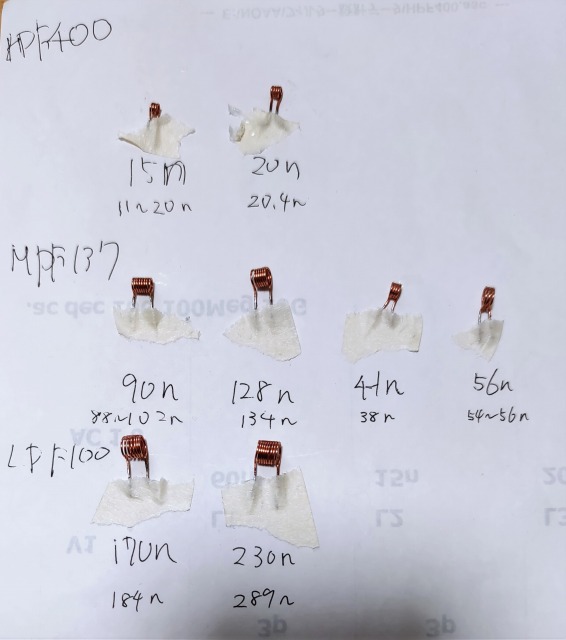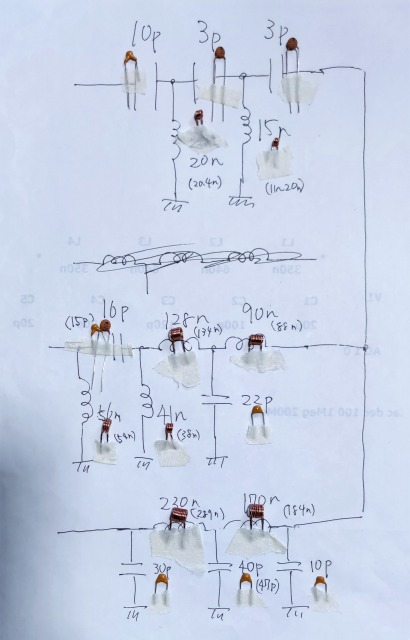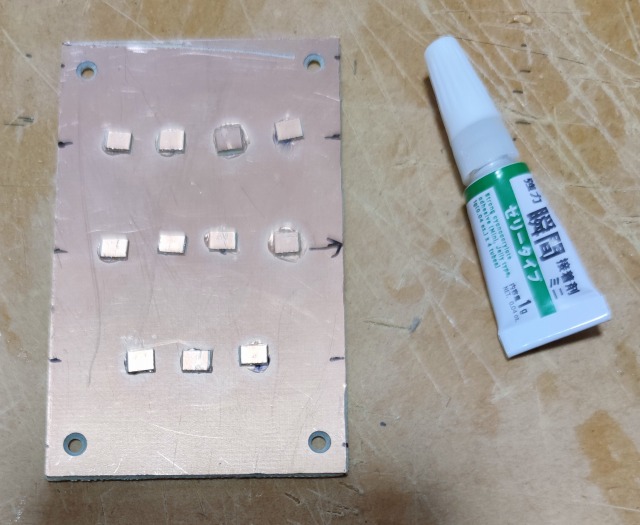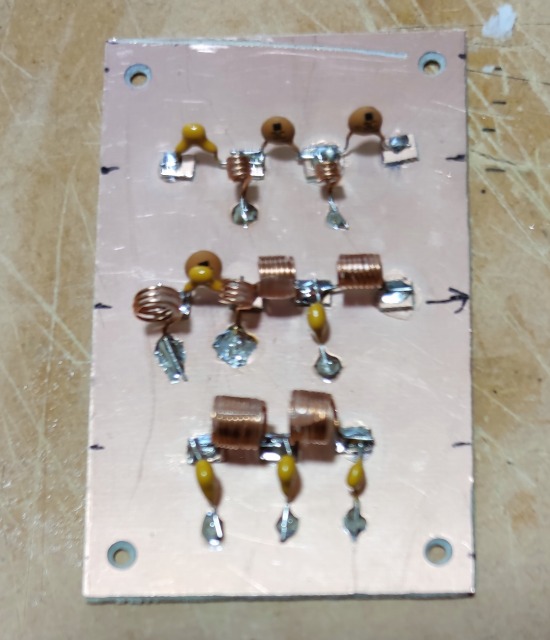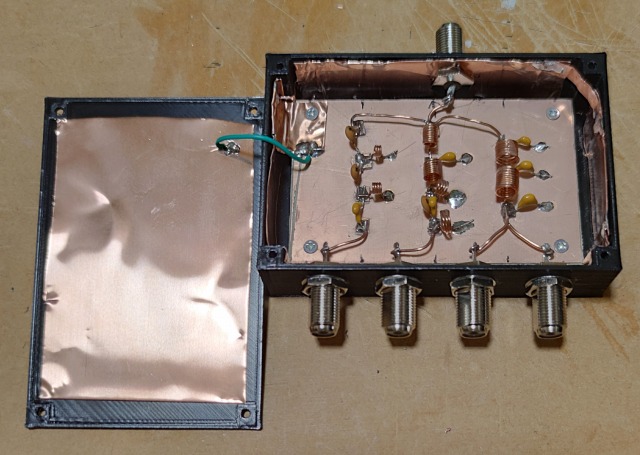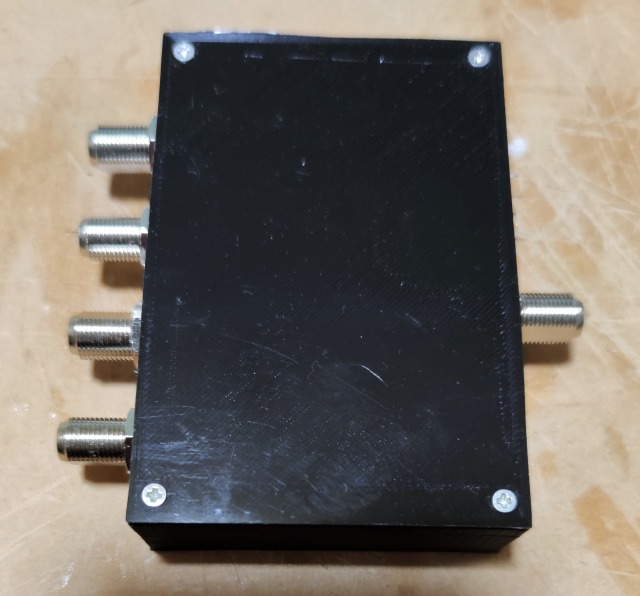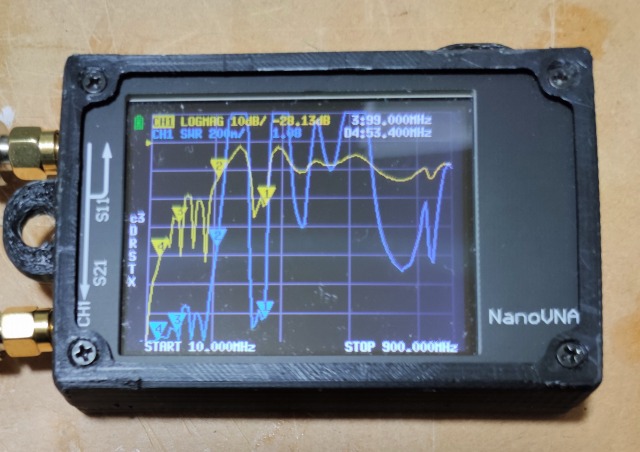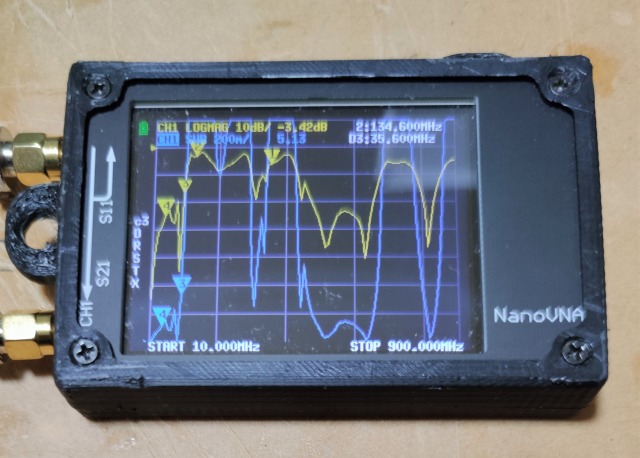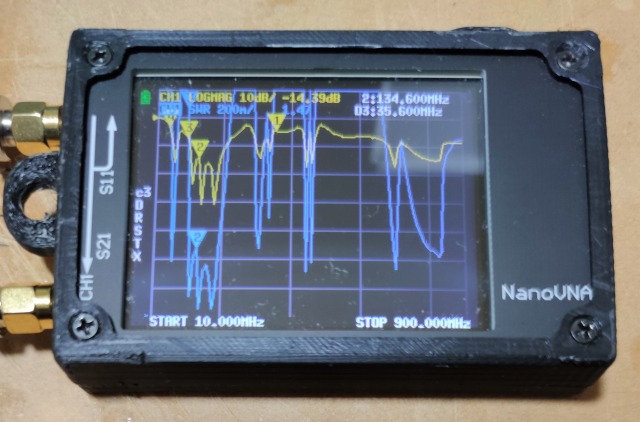NOAA+HF用アンテナを直接引き込んだ
- 2022/03/06 15:38
- カテゴリー:アンテナ
1W前からTV(地デジ)の受信状態が悪い
TVアンテナがおそらく(この時期に頻発する)強風による方向移動ようなので調査&解決のため屋根に昇った(本当は昨日にしたかったのだけど強風のため断念)
(写真を撮り忘れれたため無し)
ついでに地デジ+BSと共用にしていたNOAA+HF用アンテナを直接引き込んだ
ケーブルはエアコン口から屋根を経由,エアコン口は狭いためRG174を使用し宅内はRG174を使うが宅外は4CFBで繋いだ
NOAA+HF用アンテナも近い位置に変更(もう少しは短縮できそうだが,4CFBを13m,RG174が8mになった)

これで7MHz帯のアマチュア無線も受信可能になる(マグネチック・ループアンテナだけど簡単な割に結構頑張る)
NOAAの受信も良好
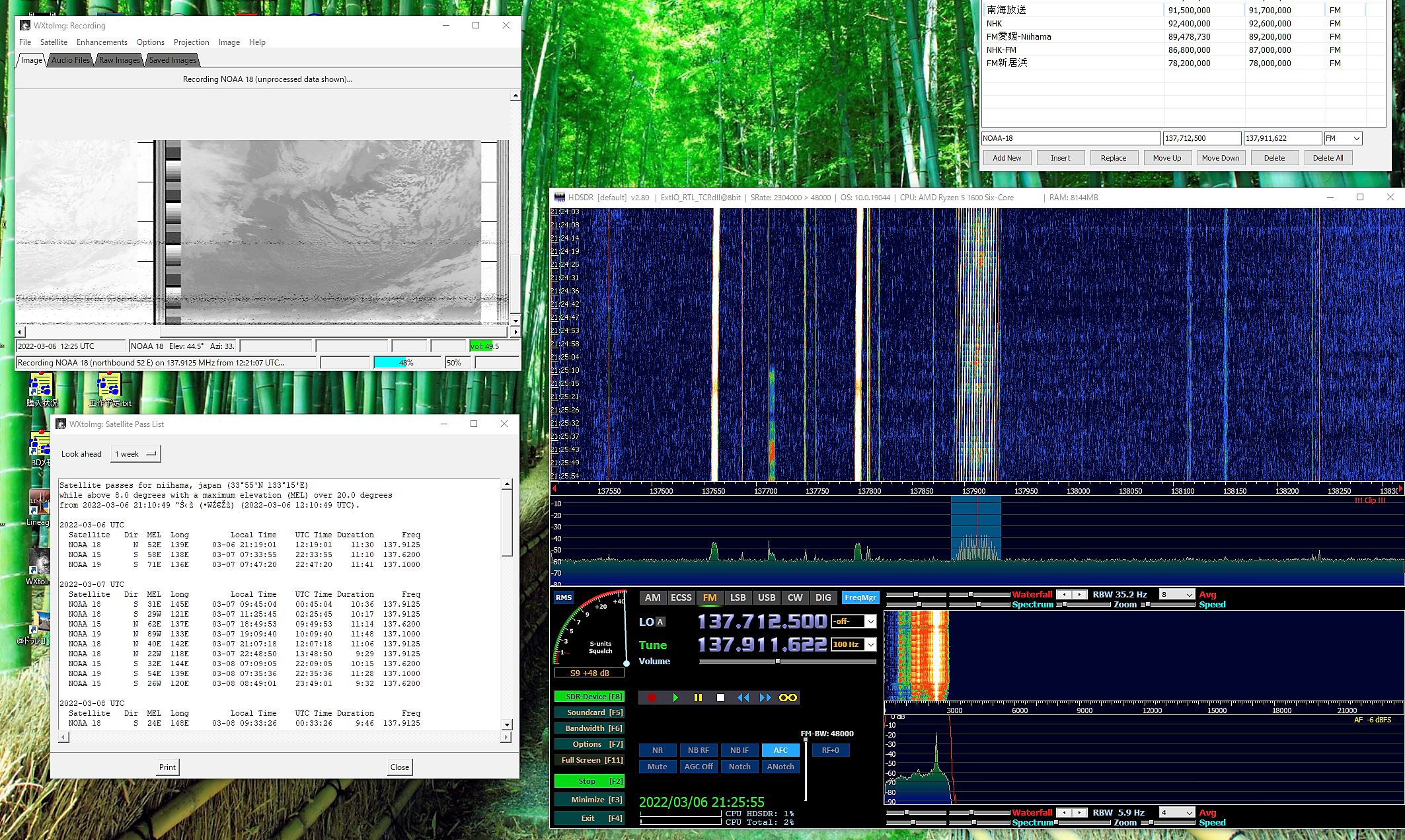
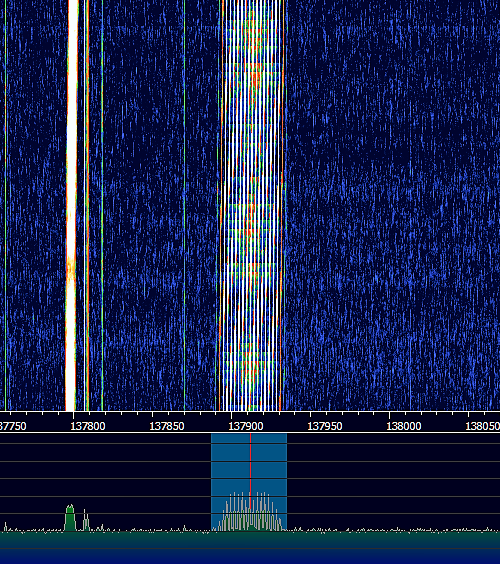
NOAA受信結果(21:19~21:35)
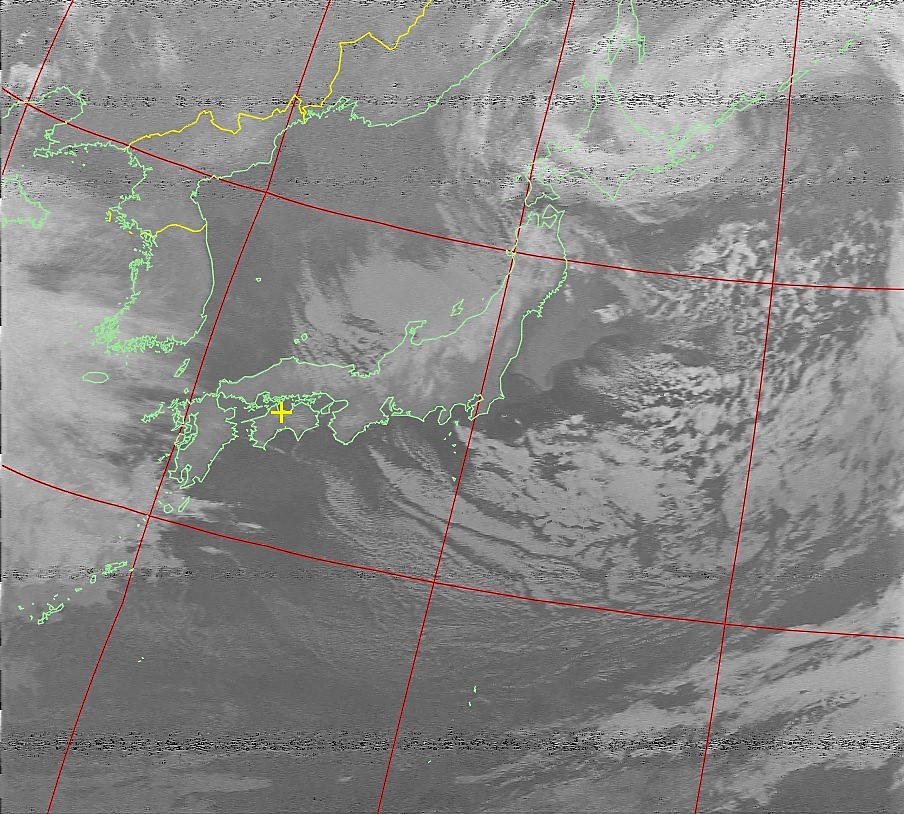
今回の受信はAliexpressで安く購入したRTL2832で試してみた

TCXO 0.5PPMとなっているが本当か?と思って確認
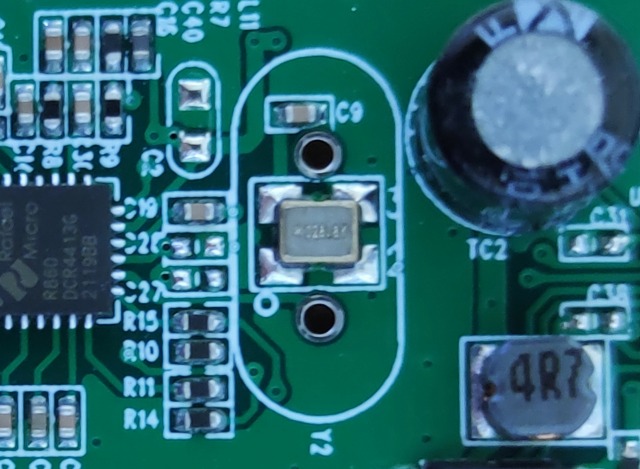
ちゃんと変更されていた(¥1,706なので,これはお買い得)
ちなみに例の類似品は+40kHzズレがある